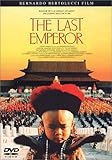
清朝最後の皇帝・愛新覚羅溥儀の生涯を描いた大作ですが、登場人物のキャラクターが全く史実に反している点が大きな問題です。例えば、主人公の溥儀は、日本人なら大概の人が知っている通り、有名なゲイ(男色家)だったのに、映画の中では平凡なヘテロ(異性愛者)として描写されているのは、いったい如何なる理由からなのでしょうか。本人も近親も認めている事実を、このように歪曲して表現することは、死者に対する一種の侮辱ではないでしょうか。また、甘粕大尉を「悪役」だからという理由で、監督が平気で身体障害者に仕立て上げているというのも、どう考えても不当な「差別的行為」であるとしか言えません。他にも色々と問題点は指摘出来るものの、映像の美しさといい、衣装・髪型の素晴らしさ(もち!ろん「西洋人のオリエンタリズムないしシノワズリーでしかない」と言えましょうが)といい、決して凡百の駄作ではありません。出来ればノーカット・完全版で見て貰いたい作品です。

20数年前の作品なのに、古さを全く感じさせない。
長丁場になるも疲れないし、飽きない。
現在と過去を幾度も行き来するが、転換が自然で煩わしくない。
壮大な流れに翻弄されるひとりの男、溥儀を淡々と描いて軽妙。
まるで皇帝本人のように淡白にして気品漂う作品だ。
映像美と構成力と演出ゆえか。
贅沢をいえば、溥儀自身の性癖や矛盾に踏み入ることができれば、
この大作にさらなる芳醇さと深みを与えると思うのだが。
また全篇英語で通されると、欧米の視点やハリウッド受け(例えばアカデミー賞)
など余計な雑念が湧き上がって耳障りだ。
20数年前に中国語を話す人々を使ってこんな映画を創ること自体、
不可能だろうが、その国特有の題材はその国の言語に支えられてこそ
深く響くことを思えば、中国語でリメイク版を観てみたいものだ。

清朝最後の皇帝、溥儀の帝師による清朝最後の日々から満洲国成立までの回想記。東京裁判で証拠提出も棄却され、岩波から出版されたものでは大幅カットされていたいわくつきの書である。
監修の渡部昇一氏の指摘するように、中国の当時の政治状況を知る上で第1級の史料である。自身の経験や関係者の証言、新聞報道や街の声などがバランスよく巧みに織り込まれ、客観性を担保している。
宮廷内の様子や政争、皇帝の人柄まで、歴史の証人だからこそ再現できる臨場感がある。
革命や動乱に揺れた中国近代史の理解が深まることは間違いない。

言うまでもないが英人R・F・ジョンストンがまさに消えゆく満洲王朝(タイトルの由来はそこから)と宣統帝の帝師としての実体験をつづった名著である。
すでに国内に邦訳は戦前から4冊出ているがすべて初版本を基にしたもので、注はほとんど省かれた不完全なものだった。
渡部昇一氏と中山理氏が『完訳 紫禁城の黄昏』を出したが、これも初版本を基にしたものなので原著の間違いをそのまま訳してしまった。
この「新訳 紫禁城の黄昏」は、原著の間違いをジョンストン自身が修正してだした第4版を基礎にしており、なおかつ訳者の岩倉光輝氏が原文の固有名詞の間違いを修正したものである。
訳文は現在出ている他の邦訳に比べて読み易く、表現も理解しやすい。

簡単に書くと、関東軍主導で建国された傀儡満州国。その関東軍と皇帝溥儀との会談録。外務省派遣の溥儀お抱え通訳・林出氏が詳細に記録し外務次官等宛に内密にこの会談録を送っていたのが出てきて、それを筆者が短く読み物としてまとめた本。って感じ。会談録そのままの文章や、溥儀の「我が半生」からの引用も含め史実との相違が浮き彫りにされている。皇帝溥儀が決して口外できない様々な「密約」の数々などなかなか興味深い。
…関東軍(日本)が清国宣統帝・溥儀を利用し(中国東北部)とどのような関係を築きたかったのか。それがダイレクトに見える。と感じた。
| 