
アンドレイ・ルブリョフ [DVD]
この映画は、ロシア中世の聖像画家アンドレイ・ルブリョフの半生を、想像の物語として描いた作品である。監督のアンドレイ・タルコフスキーは、詩人アルセニー・タルコフスキーの息子で、日本文化に深く傾倒して居た事で知られて居る。
旧ソ連は、巨費を投じてこの映画をタルコフスキーに製作させたが、完成した映画の内容は、その反体制的な内容からソ連当局の怒りを買ひ、1966年の完成後、ソ連国内では事実上上映禁止の状況に置かれる事と成った。その『アンドレイ・ルブリョフ』が、西側で知られる事と成ったのは、当時のフランスの文化大臣アンドレ・マルローが、この作品がカンヌ映画祭で上映される様尽力した事が大きいと言はれて居る。
1974年、この言わくつきの映画が日本で公開された時、私は、これを東京の映画館で観る幸運を得た。以来、今日に至るまで、この映画は、私の人生最良の映画である。−−あの鐘造りの若者の物語と、その後にヴャチェスラフ・オフチンニコフの音楽と共に画面に現れるルブリョフのイコンには、何度見ても感動を禁じ得ない。一枚の絵の陰に、歴史に埋もれた人々の悲劇と苦難が有った事を、この映画の末尾の部分は教えてくれる。−−私は、この映画は、世界映画史上最高の作品であると思ふ。この映画に出会へて、私は幸福であった。
(西岡昌紀・内科医/タルコフスキー没後20年目の日(2006年12月29日)に)

アンドレイ・ルブリョフ [DVD]
13世紀初頭のロシアが舞台。ルブリョフという当時すでにイコン画家として著名だった修道者が主人公で、映画のはじめのほうで脇役修道士の口を借りて、ルブリョフはたしかに腕がいいけれど、「虚飾を廃する単純さ」に欠けている、と評される。
その単純さに欠けて、いわば複雑な、ドロドロした情念から自由ではないルブリョフが、歴史にさらされ、さまざまの出来事に巻き込まれて、削られ砕かれてながら、単純さを有するにいたる過程が、連作オムニバス形式に描かれている。
見終わって思い出すのは、暗い顔してイコンを描く絵描きたち(修道者たち)の姿。描いたイコンを異教徒の暴徒に壊され燃やされてしまう絵描きたちの姿。異教徒の軍隊に殺されそうになり、縛られ転がされる絵描きたちの姿。雨と泥にまみれながら次の仕事場へと旅をつづける絵描きたちの姿。腕のいい同僚への嫉妬に苦しみ、よい腕を持ってもなお魂の平安には遠い絵描きたちの姿。重たいのだけれど、不思議なすがすがしさをも感じるのはなぜだろう。
ルブリョフがついついほうっておけずに構ってしまう相手として、知的障害をもつ、ほとんど口の利けない娘が登場する。異教徒たちが嘲笑しながら馬肉などなげてよこすと、大喜びで食べたりするあわれな娘である。ルブリョフ自身は、映画の後半で、みずからを罰して沈黙の行にいそしむ。『鏡』や『サクリファイス』でも言語障害の子どもが登場するが、「口がきけない」「言葉を失っている」というのは、タルコフスキーの作品の何か重要なモチーフを表しているようだ。
この映画はほとんど全編が白黒映像で、ただ最後にルブリョフが描いた有名なイコンのいくつかが、カラーで映されている。「虚飾を廃する単純さ」を感じる、厳粛な祈りのようなイコンであった。
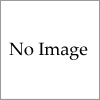
タルコフスキーとルブリョフ
−−伊勢丹前の新宿文化劇場で『アンドレイ・ルブリョフ』を見たのは一九七四年(昭和四十九)年十二月八日でした。戦中派の私にとっては、日本がハワイ真珠湾の空襲を開始した日に当たっていたことと、翌日、田中内閣に代わる三木武夫内閣が成立したことで記憶に残っているのです。ああ、もう二〇年もたったのかと、おどろきを禁じえません。(本書273ページ「あとがき」より)−−
本書の著者落合東朗(おちあいはるろう)氏は、1926年北海道に生まれ、1945年7月、満州のハルビンで関東軍に入隊、シベリアに抑留された後、帰国して早稲田大学でロシア文学を専攻した著述家である。氏は、ロシア正教に関心を持ち、ロシアのイコン(聖像画)に魅了されて居たと、本書の「あとがき」に有る。本書は、その落合氏が、タルコフスキーの傑作『アンドレイ・ルブリョフ』(1966年)の内容をシナリオに照らして検証しながら、当時のソ連の体制から考えれば驚くべき内容の作品であったこの傑作が撮影、製作された際の舞台裏を述べ、検証した研究書である。
本書を読んで興味深かった事の一つは、『アンドレイ・ルブリョフ』が撮影、製作されるに至った背景に、文芸界の自由派を批判した事で知られるイリイチョフ氏が、この作品の撮影にゴーサインを出した張本人だったと言ふ逸話であった。(本書93−94ページ参照)『アンドレイ・ルブリョフ』の中の科白通り、「ロシアは不思議の国」である事を痛感した。
(西岡昌紀・内科医/タルコフスキーの命日に)









